(イ)消費者重視の姿勢を具体化しているか
a)消費者の声を把握し、それらを経営に反映していることを明示しているか
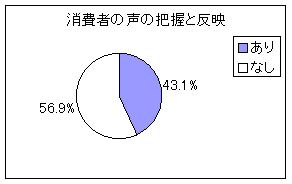
明示 25社(43.1%)
25社(43.1%)が消費者の声を把握していることを表明し、
中には積極的に商品・サービスなどに活かしていることをアピールしている
ケースも数多く見られた。
このほかにお客様窓口のみの記載が9社あったが、上記にはカウントしていない。
消費者の声の把握の意思は感じられるが、企業としてどのようにそれを生かそうとしているのかが
見えず、消費者重視の姿勢かどうかが不明だからである。
また消費者の声の把握と経営への反映については、
実に企業の特徴が出ていることがわかった。
抽象的に「お客様の声を承っています」とのメッセージにとどまるものから、
具体的な取り組みの実態を積極的に開示しているものなどさまざまである。
積極的な試みの例は次のとおりである。
●お客様窓口に入った相談件数や相談内訳の記載(味の素、キリンビール、サントリーなど)
●お客様の声を活かした商品の改善例の記載(日清食品、味の素など)
●お客様の意見や提案を事業活動に活かす流れ図の提示(伊藤園など)
|
b)安全性などの消費者の不安や関心に応えているか
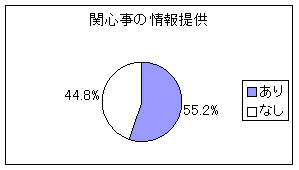
明示 32社(55.2%)
消費者重視の姿勢の具体化の中で最も多い55.2%の数値となった。
食にかかわる不安や関心、さらには食をめぐる不祥事等の事件の多さを反映し、
企業として対応を迫られている状況がうかがえる。
情報提供例は次のとおりである
●BSEの安全性について
●アレルギー表示、食物アレルギーについて
●遺伝子組み換え大豆について
●コレステロールについて
|
c)品質管理・安全確保の仕組みを明示しているか
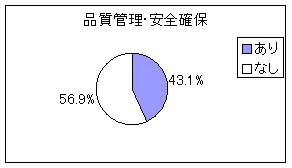
明示 25社(43.1%)
多くの企業が安全性や品質保証体制を強調して記載をしていたが、
抽象的な記載が多いのが特徴であった。
しかし、単なる安全の強調や品質保証ではなく、
次のような具体的な取り組みを明記していたケースも見られた。
●「品質保証憲章の策定」(日本水産)
●「品質保証委員会の設置」(ニチレイ)、「製品法令・表示監視委員会の設置」(昭和産業)
●「肥料・農薬の適正な使用基準の策定」(伊藤園)
|
d)不利益情報の開示がなされているか(「自主回収における結果報告の開示」)
不利益情報については、苦情情報などさまざまなものがあるが、
今回は食品関連企業の商品の自主回収が数年前から増加していることから、
「2002年度に商品等の法令違反や消費者被害に関連して商品等の自主回収を行った企業が、
お詫び広告を出した後に、自主回収した結果や広告で約束した改善結果などについて、
消費者に報告」をしているかどうかを調査した。
自主回収は法令での命令でなく自主的に回収をした事例であり、
そのこと自体は評価すべきであるが、現状においては自主回収があまりにも多く、
毎年繰り返されることも稀ではなく、自主回収が企業のイクスキューズになっている嫌いがある。
自主回収することのみで消費者の信頼獲得に役立っているとは考えられない状況にある。
また自主回収した事例の多くは消費者の権利や利害に関わる事例であり、
それらの結果について消費者は強い利害関係をもつことから、
それらの結果について知る権利をもつと考えられる。
そこで、消費者の信頼獲得の具体的取組みとして、回収率や被害回復の状況、
あるいは約束した改善への取組みをどのように実現したのかを報告しているかどうかを調査した。
なお、調査にあたっては、新しい年度では結果が出ていないこともあることから、
2002年度の自主回収事例を取り上げ、それらが2002年から調査開始月の2003年1月までに
報告しているかどうかを確認したものである。
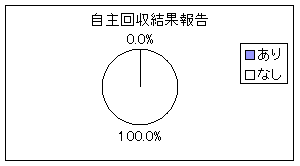
・2002年度自主回収をした企業 58社のうち 35社(60・3%)
・結果報告をした企業 35社のうち 0社(0.0%)
調査対象企業の58社の実に60.3%である35社が2002年に自主回収を行っている。驚くべき多さである。
自主回収については上述したような結果報告を実施した企業は、残念ながら1社もなかった。
企業は保健所等行政機関には報告を行っているはずであるが、
一番影響を及ぼす消費者にこそ情報提供すべきではないだろうか。
また自主回収を実施した企業の中には、自主回収したこと自体をニュースリリースから
抹消しているところもあり、PR情報はどんなに古くなっても残していることを考えると不自然であり、
むしろ企業の消費者への情報開示の姿勢に疑問を感じる例もあった。
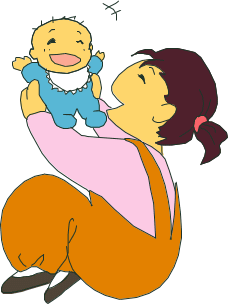

|